2010年07月17日
夫婦共働きの妻の死亡保障
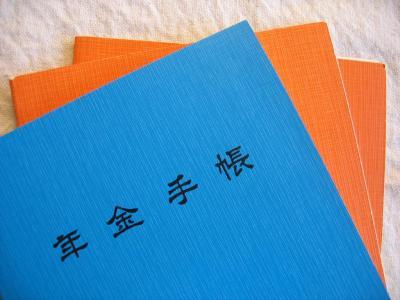
本日、2回目の保険相談のN様は、奥さまの保障の見直しにお越しいただきました。
現在加入中の保険は、奥さまのご両親が掛けてくれていたもので、それをそのまま引き継ぐかどうかをご検討されていました。
また、奥さまのご友人が2人も若くして癌で亡くなってしまった事から、がん保険の加入もご検討されていました。
前回のご相談では、奥さまとしては死亡保障よりも入院やがんの保障を充実させたいとのご要望でしたので、まずは万が一のがんや入院に備えるためのお話をさせていただき、本日2回目の相談で万が一の死亡保障についてお考えいただきました。
奥さまは今まで死亡保障はそれほど必要ないと思っていたそうです。
でも、夫婦共働きで公務員の奥さまはご主人さまと同じぐらいの所得があり、日々の生活や住宅ローンの返済のためには奥さまの収入はとても重要です。
現在住宅ローンの支払いは住宅ローン減税活用のため夫婦共有名義で返済しているそうですが、団体信用生命にはご主人さま名義で加入しているそうです。
もし万が一奥さまが亡くなってしまったら・・・
住宅ローンは丸々残ってしまうのに、奥さまの収入はバッサリとなくなってしまいます。
それに加え、日々の生活費にお子さんの教育費をご主人さま1人の収入で賄っていかなければいけなくなります。
さらに、お国の保障である遺族年金は、、、
実はご主人さまは受け取る事ができません。
まず、遺族基礎年金の受給権は“妻”と“子”だけです。
“夫”に受給権はありません。
しかし、“子”も“夫”(父親)と一緒に暮らしている場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
さらに、遺族共済年金の受給権は、この家庭の場合の“子”だけです。
“夫”が遺族共済年金を受け取るためには、“妻”が亡くなったときに55歳以上である必要があります。
夫が亡くなった場合であれば、妻は遺族年金を受け取れるのに、妻が亡くなった場合は夫は受け取る事ができません。
N様のケースであれば、お子さんが18歳になるまで遺族共済年金から毎月約6万円が支払われ、”お子さんが”受け取ることはできます。
N様は今まで奥さまの死亡保障はそれほど必要ないと考えていたそうですが、実はとても重要だと気付かれたようです。
夫婦共働きの場合の女性の死亡保障は、しっかりと考えておく必要がありますね。
2010年01月16日
妻が亡くなった場合の遺族年金は?
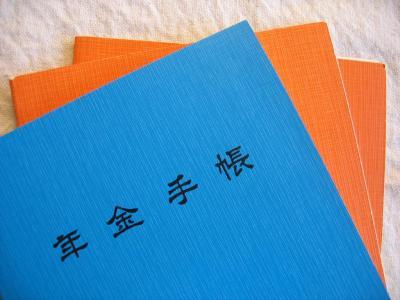
まつもと保険相談センターに相談に来られるお客様の中には夫婦共働きというご家庭も少なくありません。
まずは、一家の大黒柱のお父さんの“もしも”に備えて、保障の必要性や保障金額、保障期間等を一緒に確認いただき、更にお国の保障制度である遺族年金や勤務先の福利厚生なども考慮します。
その遺族年金とは、、、
ご主人様がサラリーマンの場合、毎月のお給料から天引きされている厚生年金保険料は、ほとんどの方は65歳から老齢年金として受け取りますが、不幸にもそれ以前に亡くなってしまった場合には、遺族年金として遺されたご家族が受け取ります。
例えば、ご主人様35歳(サラリーマン:年収500万円)、奥様32歳、ご長女5歳、ご長男3歳のご家庭の場合
万が一ご主人様が亡くなってしまったら、
①遺族基礎年金から103,992円がご長女が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
②遺族基礎年金から85,000円がご長男が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
③遺族厚生年金から約52,000円が奥様が65歳になるまで毎月支払われます。
④遺族基礎年金の支払い終了後は、遺族厚生年金から中高齢寡婦加算が約50,000円奥様が65歳になるまで支払われます。
つまり、35歳でご主人様が亡くなってしまった場合には、
①から1,622万円が、
②から204万円が、
③から2,059万円が、
④から1,020万円が、
トータルで約4,905万円が遺族年金として国から支払われます。
サラリーマンの場合、年収や年齢、お子さんの人数によっても違いますが、国からの保障がそれなりにありますので、これだけでは足りない分を、生命保険でカバーします。
では、同じように一家の生計をたてるため働いている奥様の場合は、ご主人様と同じような国の保障があるのかというと、実は全く違います。
例えば、ご主人様35歳、奥様32歳(会社員:年収450円)、ご長女5歳、ご長男3歳のご家庭の場合
万が一奥様が32歳で亡くなってしまったら、
①遺族基礎年金は支払われません。
②遺族厚生年金から約40,000円がご長男が18歳の3月末になるまでまで毎月支払われます。
トータルで約720万円が遺族年金として国から支払われます。
まず、遺族基礎年金の受給権は“妻”と“子”だけです。
“夫”に受給権はありません。
しかし、“子”も“夫”(父親)と一緒に暮らしている場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。
さらに、遺族厚生年金の受給権は、この家庭の場合の“子”だけです。
“夫”が遺族厚生年金を受け取るためには、“妻”が亡くなったときに55歳以上である必要があります。
同じように厚生年金の保険料を納めているのに、男性の場合と女性の場合では国からの保障は驚くほど違います。
女性の死亡保障は見落としがちですが、実は働く女性の保障はとても重要です。
2009年12月20日
妻が亡くなった場合、夫は遺族年金をもらえない?
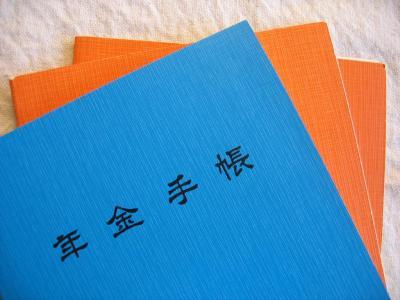
本日、まつもと保険相談センターにお越しいただいたS様は、月々の保険料を安くしたい、でも保障金額は下げたくないとの要望でした。
まずはご主人様の保障の見直しをさせていただきました。
万が一ご主人様が亡くなってしまった場合の遺族の生活費や教育費等の必要保障額を一緒に確認させていただき、次に国からもらえる遺族年金についても、万が一の際にいくらぐらい貰えるか確認させていただきました。
ご主人様は公務員ですので、万が一の時には遺族基礎年金に加え遺族共済年金を奥様は受け取ることができます。
そこで、遺族年金だけではたりない保障額を生命保険でカバーするということで、ご理解いただき、見直し提案をさせていただいたところ、現在より保障が厚くなり、保険料は安くなり、S様に大変喜んでいただきました。
さてさて、次は奥様の保険の見直しです。
下のお子様が5歳になったので、奥様は職場復帰し、現在夫婦共働きです。
奥様の収入も家計をしっかりと支えているため、万が一奥様が亡くなってしまえば、遺されたご主人様とお子様2人は今までと同じような生活はできなくなります。
したがって、奥様の万が一に備えて死亡保障も考えておきたいとのご要望でした。
ご主人様と同じく、奥様も公務員です。
当然、共済年金の保険料は毎月給料天引きで払われています。
それならば、ご主人様の時と同様に遺族年金と遺族共済年金が遺族(夫、子)に払われるのかと思いますよね?
ところが、遺族年金は夫と妻では同じ扱いではないようです。
まず、
「遺族 基礎年金」は妻と子だけがもらえます。夫はもらえません。
そして、
「遺族 共済年金」の受給権があるのは、
(1)妻
(2)18歳未満の子、孫
(3)55歳以上の夫、父母、祖父母、です。
しかし、夫が遺族共済年金を受け取れるのは60歳からです。
遺族年金は、家族に万が一のことがあった場合に残された遺族の生活を国が保障する制度であるにも関わらず、亡くなったのが妻の場合は、例え夫婦共働きであったとしても、同じ保障を受けられません。
したがって、夫婦共働きの場合は、奥様の死亡保障もしっかりと考えておく必要がありますね。
本日のS様も、ご家族のためにご自身の保障をしっかりと考えておられました。
それにしても、、、
妻の年金の保険料は、いったいどこへ行ってしまうのでしょう??





